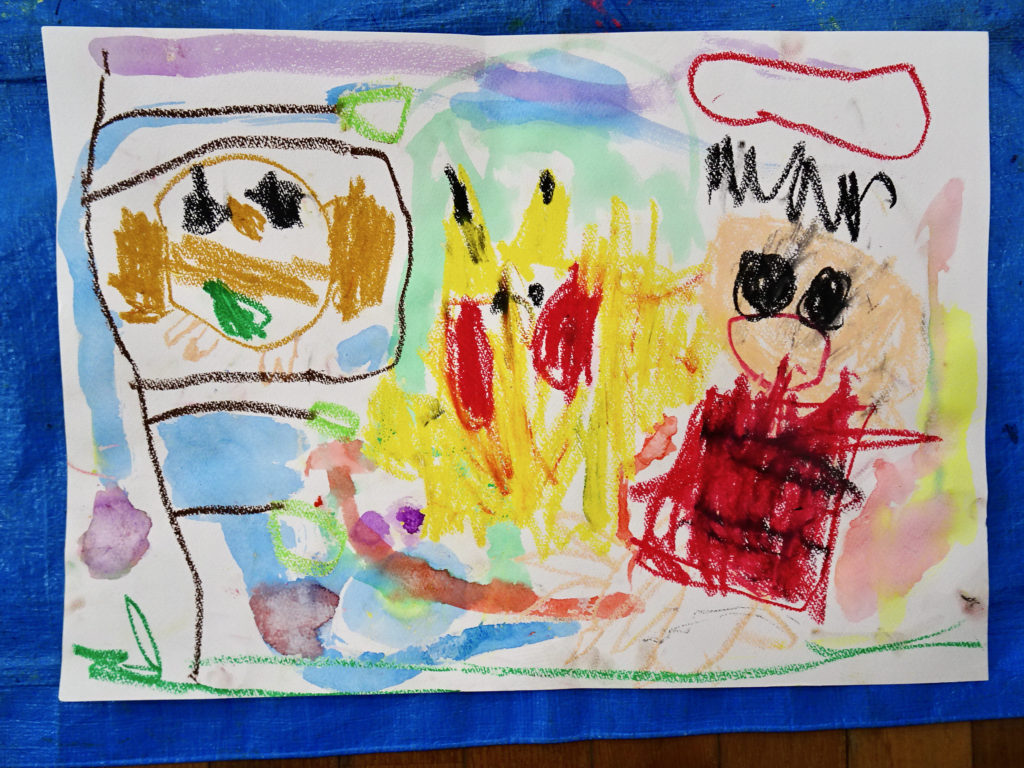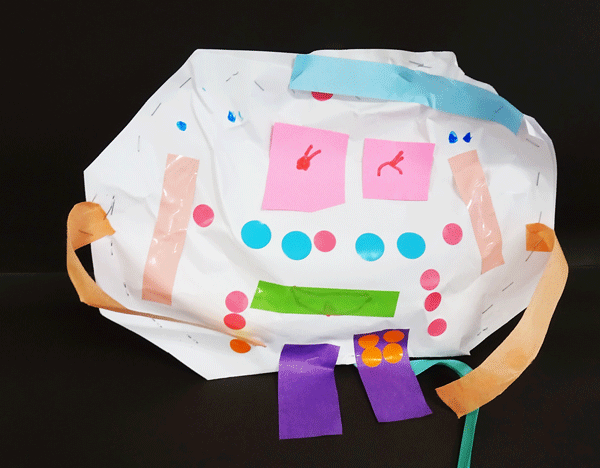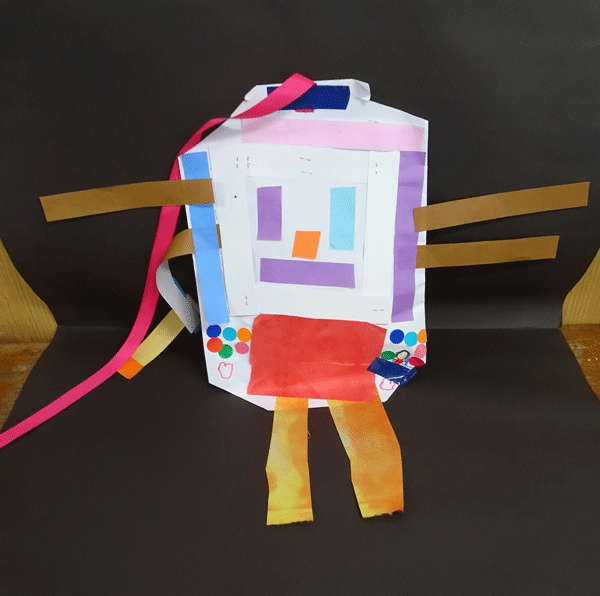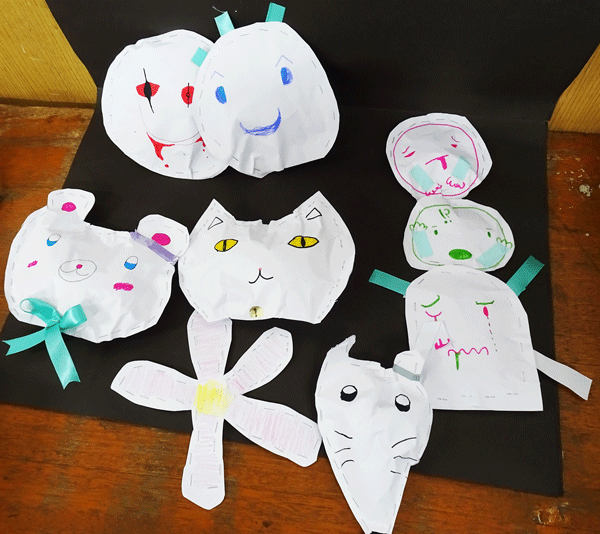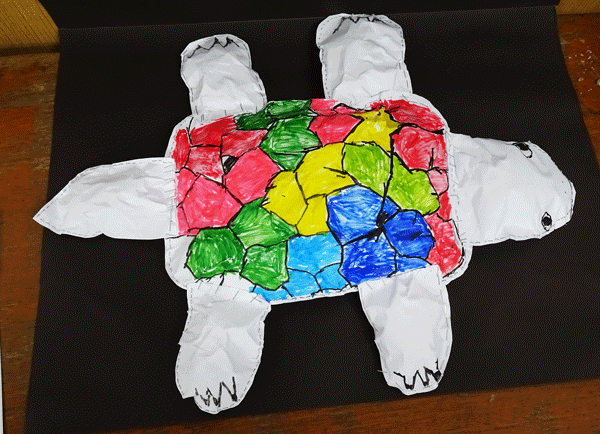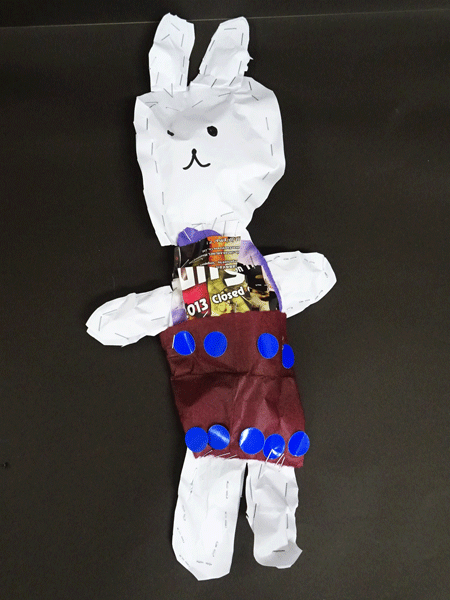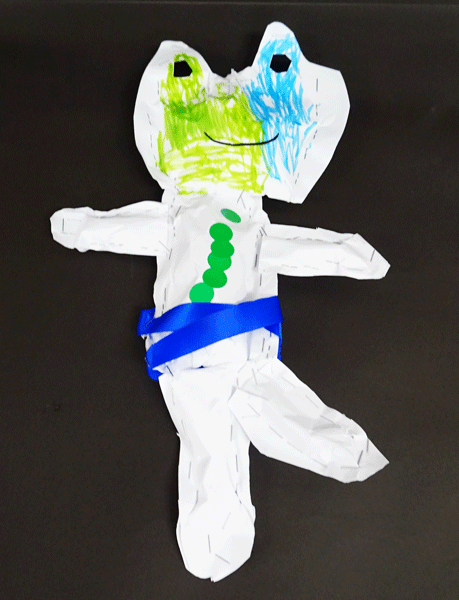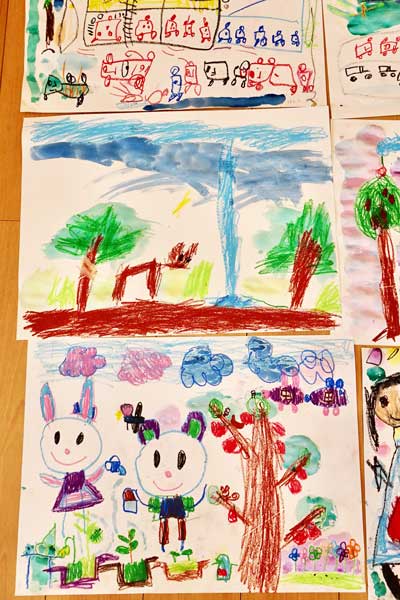3さい「小さい紙に描こう」
A4のコピー紙¼くらいの紙のサイズに
気軽にどんどんお絵描きしよう!という遊びです。
お絵描きは、好きな子は自由帳などにどんどん描いて
描くことの楽しみに触れる機会が多くなるのですが、
そうでない子は、描く機会自体から遠ざかってしまって
より苦手意識や楽しみに気がつかなくなってしまう
ということになりがちです。
とにかく気軽にらくがきを楽しめるようになると
描くという「表現方法」の可能性に気が付くきっかけになります。
今回の活動は、描いた後に自由に飾れるのがポイントで
飾るという「遊び」に後押しされて、普段あまり描かない子も
結構何枚も描いてくれます。
まだ色をグルグルしただけの子もいますが、そういう子も誇らしげに
飾った絵のことをお喋りしてくれます。
3さい、4さい、5さい、学年それぞれに楽しめますよ。
4さい「スクラッチ技法遊び」
クレヨンでカラフルに塗りつぶしたところに
黒いクレヨンでまた上塗りして、それを削る遊びです。
絵本の題材にもなったり、昔から定番の遊びですね。
遊ぶ時のコツは、下に塗るカラフルな色を、しっかり塗ることです。
子ども達は隙間なくしっかり塗るというのは
慣れていないとなかなかできないので
丁寧に教えてあげながら頑張ってみてください。
後で綺麗になるぞ!という楽しみを理解してもらうことも大事かもしれません。
削ってからまた黒で塗りつぶすと何度でも引っ掻いて遊べますよ。